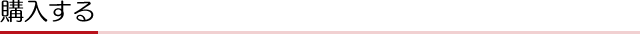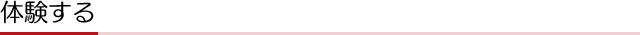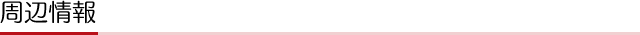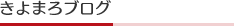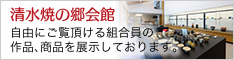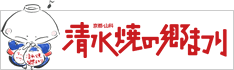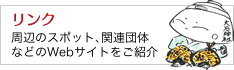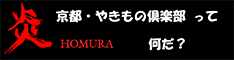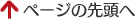京都山科・清水焼の郷 清水焼団地のホームページ。清水焼・京焼、清水焼の郷まつり(陶器まつり)の情報などを発信しています。
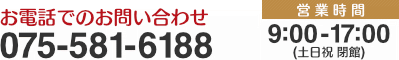
昭和の高度経済成長は急速な社会情勢の変化をもたらし清水・五条坂周辺は市街地化、観光地化が進むことで登り窯の煤煙についても懸念されるなど都市部に形成された産地ならではの問題を抱えるようになります。そんな中、新しい事業展開を模索するなか新天地を求め有志が集まり住居と工房を併せた工業団地として清水焼団地が誕生しました。
清水焼団地は、京焼・清水焼の問屋、窯元、作家、原材料屋、指物師、碍子関係など“やきもの”に関連する業者が連なっております。
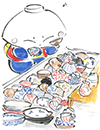
江戸時代より京都のやきものは華麗な色彩や繊細なデザインをもつ多種多様なやきものが生み出されてきたことで高い評価をえました。野々村仁清や尾形乾山、奥田頴川、青木木米など名工たちも個性あふれる優品を数多く残しています。その優れた意匠と高い技術を育む伝統は今日まで受けつがれ、京焼・清水焼は現在も一つ一つ職人の手で丹精を込めて作られております。京焼・清水焼の生産地で散策しながらお買い物を楽しんでください。清水焼団地内の店舗については、組合員のご紹介ページをご覧ください。
※オリジナル陶磁器の受注製作も承っておりますので、ご相談ください。
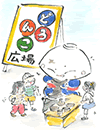
手び練りや絵付け体験など陶芸体験も受け付けております。詳しくは、組合員のご紹介ページをご覧ください。不明な点などございましたら清水焼団地協同組合へお電話(075-581-6188)またはメールフォームよりお問い合わせいただけましたら幸いです。

清水焼団地の周辺観光地スポットをリンクのページにてご紹介しております。
是非、観光地と併せて清水焼団地へもお越しください。