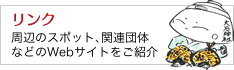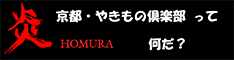父親で日展作家の寺池陶秌 (てらいけ とうしゅう)氏のもとで育った寺池静人さんにとって、陶芸の道をめざすことは自然なことだったという。
「小学校を出たのが終戦の時。空襲で家も焼けてしまった頃でしたから、建築科に入った方が有望だと親父にも言われました。でも、そのころから陶芸に進もうと自然に思っていましたね。父親は絵付けが中心の仕事でしたので、形を勉強した方がということで、彫刻科に進みました」
卒業後は、訓練校でろくろを学び、楠部彌弌先生に師事。楠部先生にまず問われたのは「どういうつもりで作陶するのか」だった。寺池さんは迷うことなく「今までにない焼きものを作りたい」と答えたという。
「中国、朝鮮、日本と過去に様々な作品が作られている。そういう過去の作品と違うものを作ることで、自分の存在感を出せると考えていたんです。すると、楠部先生から『人間をつくれ』をといわれて」
「人間をつくれ」。それはどういう意味なのかと尋ねても、楠部先生は「自分で考えろ」と言うばかりだった。この言葉は、寺池さんの作陶人生に関わる大きな一言となった。 それから30年ほどが経ち、個展の報告にいったときも、楠部先生にはまだ「人間を作れ」と言われたという。その時に、一冊の本を託された。本の中に、「ものを作るということは、結局人間を作ることである」という言葉が書かれていた。
「それをものづくりの極意やといってくださったんです。人間を作らんといいものができないと。作る人間のその時その時の感情が、作ったものに現れるから、常に平常心でものをつくる。先生の言葉はそういう意味やとようやくわかりました。今も、一生の言葉だと思っています。死ぬまで人間作りを追い求めていかなあかんなと思っています」
寺池さんの工房は、椿、カトレア、牡丹といった美しい植物たちであふれている。それらの花々をレリーフで刻み、蕾を形にかたどって作り上げられるのが寺池さんの作品だ。
「釉滴彩」という独自の釉薬を施すと、花びらが水滴を帯びたような印象を与え、光が反射するたびにみずみずしい輝きを見せる。
「花のスケッチをしていたときに、突然雨が降ってきてね。しばらく雨宿りをして雨が止むのを待っていると、太陽がさっと出て、水滴をきらきらと輝かせたんです。それがなんとも言えず綺麗でね。それを表現したいと思い、釉薬を作りました」
絵付けで花を描くのではなく、彫刻科で学んだ経験を生かして陶器の表面に花々をヘラで彫刻していくのも、寺池さんの作品の特徴だ。花びらもそのまま写すのではなく、装飾性を考えながら自分流にアレンジしていく。
「失敗作というのはできるだけ少なくする。思い通りにいかなくても作品を割るというのはなかなかできませんね。最後の最後でひびが入ったとしても、それでも最後まで仕上げます。途中で失敗しても、その原因を探ることで次の作品に活かします」
人生の中で、とても苦しいことが身に降りかかることがあります。そんなとき、作品を作る手が止まることがありますが、なぜこんな苦しみが自分に襲いかかるのかと、疑問をもつのではなく、真っ暗の闇の中に、針の穴でもあかりがあるはずだと考える。光を見つけることが、試練だという風に解釈すると、自然と気持ちが落ち着いてきます。
「人間を作れ」という楠部先生の言葉の意味がわかったのは、そういう風に考えるようになってからだと思います。どんな嫌なことでもプラス面を見つける自分自身を作ること。それこそが大切なのだと、先生の言葉を通して感じながら、作品を作り続けています。