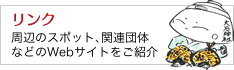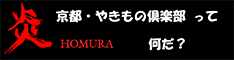手塚央さんは、陶芸家、手塚玉堂の二男として昭和9年に生まれた。次男坊として生まれた立場上、父の後を継ぐことは意識していなかったという。
「兄がいましたからね。兄は兄で父の後を継ぐだろうと思っていましたし、自分がやるとすれば、一人でやるしかないと思っていました」
後継者としてではなく、一人の陶芸家として、その道に進もうと決意したことも特にない。ただ自然に、陶芸家の道を選んだ、と手塚さんは言う。
「家が陶器やってたからね。別に志してというか、職業の選択がない時代でしたし、15歳からやってるからね」
手塚さんの作品は、中国明王朝の成化帝の治世下で開発された「豆彩」という技法で作られたものを中心としている。
豆彩は景徳鎮の国営磁器窯にて開発された特殊な色絵磁器で、文様の輪郭を染付の細い線で描き、上絵具で淡い緑色などを施している。その色合いが、空豆に似ていることから、日本では「豆彩」と呼ばれているが、中国では「闘彩」と書かれている。宮廷磁器として珍重されていたため、現存する作品は数少なく、「まぼろしの中国磁器」として、その技法を再現する陶工はほとんどない。
手塚さんは、その豆彩の鮮やかな色調に魅かれ、20年にわたり独学で研究した後、1985年に初めて再現、発表した。 技法を習得して以降は、花鳥画や魚などをテーマに、独自性にあふれた作品展開をしている。作家活動のほか、清水焼団地に「手塚祥堂陶苑」という窯元名で、弟子二人とともに、一般食器や茶器などの制作に励んでいる。
「豆彩の見た目の明るい美しさが好きですね。色を表現するには何度も焼成を繰り返し、時間かけないとできません。どんなに用事があっても一日8時間は作っています」
時間をかけて、思い通りの色に仕上げていくことに、面白みがある。
「自分の計算通りにできる。模様をつけて色をつけて焼けば、自分の考え通り、それ以上にも以下にもならないところがいいですね」
自分の計算がなければ、思い通りに行くことはできない。その理想の色や形を見出せたのは、若い頃からいい作品を見続けてきたことにあります。
いいものを見て、いいものとわかるような眼力ができてくる。それがどういう風にできているかがわかるようになり、自分の計算の中で作ることができるようになるのが面白い。いいものを見るというのは、自分自身の資質を高めることでもあるのだと思います。