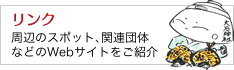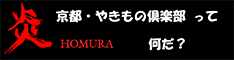パチパチパチ・・・築百年は優に超える重厚なたたずまいの町家。まさしくウナギの寝床といった奥まったところにある窯場から聞こえてきたのは、焼きあげたばかりの煌々とした茶碗に、貫入のひび割れが入る音だった。積み上げられた薪、一杯の茶碗を焼くためだけの窯… 楽焼の窯場は、非公開という印象があるが、和楽次期8代目当主川嵜基生さんは、快く案内してくれた。
楽焼の「和楽」はもともと「短冊家」といい、古くから八坂神社門前において門前茶屋を営んでいた。文政年間、当主の七左衛門は趣味から楽焼を始め、2 代目がそれを大成。茶屋をたたんで、楽焼の短冊家が誕生した。楽焼といえば茶道具が中心だが、江戸時代から鑑賞用に栽培されていた園芸品種の万年青(おもと)の鉢植えに使われる「万年青鉢」が好評で、「万年青鉢の短冊家」と呼ばれるほど評価が高かったという。5代目の時代、東郷平八郎元帥が店を訪れた際、「和楽」という名前を賜ってからは、屋号を「和楽」に改めたが、以降も人気を博した万年青鉢だけは「短冊家」の屋号をそのまま引き継いでいる。
現在は、茶道具や土鍋や向付などの食器、置物といった品々を幅広く取り扱っている。赤楽、黒楽から、楽焼の低温焼成を活かした色鮮やかな絵付けなど、店内には実に様々な品が揃う。しばらく途絶えていた万年青鉢の製作も、ここ数年前から復活している。
7代目の長男として生まれた川嵜さんは、理系の大学院を卒業後、8年にわたり東京で発電所の設計士をしていた。そのうちの6年間はドイツ、イタリア、アルジェリアなどヨーロッパの顧客との折衝を任され、海外出張も度々あり、充実した日々を送っていたという。
「小さい頃に土を触った経験もなく、家業を継ぐということは考えなかった」という川嵜さんの気持ちを変えたのは、東京に働きに出るうちに、京都の良さを再認識したこと。
「家業をこのままなくすのはもったいない、そう思いました」。
そうして、川嵜さんは33歳の時、楽焼の世界に飛び込んだのだった。
33歳からのスタートは、職人としては遅いスタートであることは間違いない。
「始めたのが遅いだけに、他の人と同じことをしていたらだめ。それよりも、8年間の社会人生活をどう活かすかを考えましたね」
そこで、川嵜さんが考えたのは作るだけでなく、自ら商品の魅力を発信していくこと。快く窯場に入れてくれたのも、そんな「楽焼の魅力を身近に感じてもらいたい」という思いからだろう。技術を習得する合間を縫って店に立ち、入ってきたお客さんには積極的に窯場を見てもらうようにする。並んでいる作品をお客さんが手に取りやすいように、飾り棚の硝子戸を取っ払う。お客さんからの質問には「相手が何を望んでいるか」を察知しながら、丁寧に答える。さらに、社会人生活で培った得意の語学力を生かして、外国人の接客にも力を入れなど、川嵜さん流に店のあり方を模索してきたのだ。
「外国には、茶道をたしなむ方も少なくない。定期的に京都を訪ねに来られる方もおられますので、そういうお客さんを相手にできたらいいなと思っています」
そういったコミュニケーションが、作品に魅力を与えていく。楽焼が昔ながらの製法を守りながら作られているところを見て、愛着を深めるお客さんもいることだろう。
「仕事場を見てもらって困るようなものでもないですし、そもそも真似をできるようなことでもない。むしろ見てもらって、興味をもってもらえることの方が、ありがたいこと。質問されれば応えるのが、私の仕事の一つだと思っています」
かつては扉をしめていた玄関も、今は解放されている。そこからは気持ちいい風が吹き込んでいた。それは、川嵜さんが起こした新しい風のようにも感じられるのだった。
窯場を公開したり、楽焼専門のお店ならではの豊富な品揃えから、形や大きさ色など、様々なお客さんの要望に応えたり…お客さんには、ここでしか味わえない体験をしていただきたい。そんな思いから、敷居の低い店づくりを心がけてきました。
それが、売上に直結するのかはわかりませんし、関係のないことなのかもしれません。
しかし、「こんな祇園からほど近い街なかで、薪使って窯を焚いていらっしゃるんですか?」「こんなにたくさんの楽焼、初めて見ましたよ」という、お客さんの声に応えていくことは、私にとって大事なこと。楽焼の魅力を身近に感じてもらうように、これからも努力していきたいと思います。