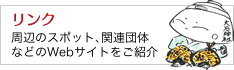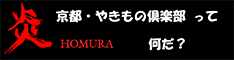昭和5年生まれの今井さんは、少年時代を疎開先の広島県竹原市で過ごした。海と山に囲まれたなかで、ひときわ好きだったのがデッサン。虫や魚、花など、瀬戸内の自然を描くのに夢中になった。学徒動員で精錬所に勤めていた時も、鉛をこっそり持ち帰っては、生き物を型どった土型にそれを流し込んで遊んでいたという。
「もちろん、持ち帰るのは内緒ですよ。防空壕で過ごす退屈な夜なんかに、そうやって遊んでたな。好きだったんでしょうな、あれこれ作ったり書いたりするのが」
今井さんが陶芸家の道に入ったのは、戦後のこと。骨董好きの父親の「日本も平和になったんやし、陶芸でもやらへんか」という言葉で決まったのだという。
「親父の言葉がすんなり頭に入ってね。陶芸やることに対しても、全然抵抗無かったんですわ」
今井さんには、父親のひとことを受け入れるだけの素地があったのだろう。“ものつくり”に対する好奇心。作品のモチーフに描かれる生き物達の姿。少年時代の精神が、陶芸という表現に受け継がれたのだ。
生き生きとした魚、花たちが踊る今井さんの作品。生き物が持つ素直な命を感じさせ、見るものの心を癒す。
今井さんは、陶芸に象嵌技法を取り入れた第一人者として、「象嵌の今井」と称される作家でもある。象嵌とは、土に別の色土を嵌めこんで焼くという技。土は焼くと縮む性質があり、その収縮率は土それぞれに違うもの。嵌める際、土の収縮率を計算しておかないと、隙間ができたりひびが入ってしまうのだ。そういう困難に加え、今井さんが挑戦したのは、面の象嵌。線を象嵌する陶器はあるものの、より嵌めこみ範囲の広い面象嵌は、今井さんが10数年もの歳月をかけて始めて実現させた分野だ。
「まさに土との闘いですわ。何度も何度も実験しては、失敗しました。それでも、面白かったんやろうね。どうやったら様々な土が上手く混ざり合えるのだろうかって、考えるのが楽しかった」
焼く窯は、登り窯。「窯変(ようへん)」という自然の窯の出す焔で土色が微妙に変化するのを狙うためだ。
「土はもともと、マグマからできたものです。地球が誕生して45億年といいますけど、再び私が土に炎を入れて、火色を焼き付けることによって、45億年前の姿に戻してあげるような気がしますね。」
「土も自然、炎も自然、デザインも自然。自然をずっと私は表現してきました。今も、スケッチブックを持って出かけます。釣りで釣った魚をデッサンしたり、花を写生したりするためです。これからも、そんな生活を繰り返しながら、自分の思いを表現していきたい。自分にとって良い陶器とは、作家の思いが表れている陶器です。その作家しかできないもの、表現できないものがあるからこそ、“1点もの”の魅力がでてくるんです。まず、作品に触ってみてください。手に取って見て、作家がどうやって作りこんでいったのか、想像させる作品。それがええ陶器やと思てます」