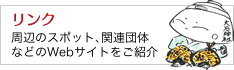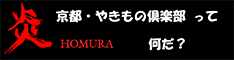器は料理の着物?美食家として、また、陶芸家として生きた北大路魯山人が語る陶と料理の関係。料理は主で、器は従。主張せず、でしゃばらず。あくまで、料理を引き立てるために器は存在するという。
「陶器はね、使うことにこそ、価値があるんですよ。実際にお金を払って買ってみて、手にとって、料理を盛り付けてみて始めて、良さがわかるんやと思うんです。」
陶花堂代表、秋山紀夫さんは話す。陶花堂は、割烹食器、抹茶碗、花器を扱う問屋。特に、割烹食器では、先付、八寸、椀物、向付・・・といった会席料理それぞれに使われる器を、季節ごと、月ごとの風合いを添えて、取り揃える。まさしく魯山人の言葉通り、春夏秋冬の季節と料理を演出する器作りが中心だ。
秋山さんは、窯屋、絵付けなど100件以上ある専門業者とともに、取消費者に合わせた器を作り出していく。陶器の形や絵柄を考えるデザイナーであったり、料亭回りをする営業マンであったり、自身、様々な役をこなす日々だ。
「“こんな形は焼けへん”と、自分が提案した器を、窯屋さんから跳ね除けられることもありますし、逆に窯屋さんがアイデアを出して、生まれる陶器もあります。絵付け専門、生地専門、沢山のプロの手が通いながら作られる陶器は、本当に試行錯誤の連続です。」
陶花堂で特徴的なのは、割烹食器を始めとする器たちが、京焼の流れを汲むものであること。京焼とは、一般的に、江戸時代に活躍した陶工、野々村仁清、仁清の弟子であり琳派の尾形乾山らが確立した色絵陶器や、唐草、法曹華といった、中国明代に影響を受けた花鳥文様=「祥瑞(しょうずい)文様」が描かれた「呉須」、「呉須赤絵」などのこと。広く愛されてきた先人たちの意匠の“写し”を陶花堂は手掛けている。
「“写し”といっても、どうやっても再現できない色があったりして、簡単にはできません。現代の科学技術をもってしても、不思議なことに、当時の色が出ないんです。それだけ、作品が秀逸だからなのでしょう。いかに、それを現代の色に蘇らせることができるか、近づくことができるかが課題ですね。また、本流から外れることなく、現代風にアレンジすることも大事です。
何が売れるのか、どんな形、デザインが今、受けるのかを思案するのですが、失敗もよくあります。自分でよいと思ったものが売れなかったなんて、何度も経験しましたよ。」
“10年経っても、まだまだ掴めない”と秋山さんは言う。それでも、追求するに足りる奥深い世界が陶器だ。
「美術館に行って実物を確かめたり、本を読んだり、会席料理を食べに行ったり・・・。勉強することで、自分を磨くことを続けています。それでも、一生かかってもわからないかもしれない。陶器には、それほど魅力があるものだと思いますね。」
高級ブランドのバッグや車がもてはやされ、陶器にお金をかける方が益々少なくなっている現代。
陶器は、外見を飾るものではなく、内で使う分、あまりお金をかけなくても目立たない存在だからかもしれません。
ただ、一度でも素晴らしい陶器というものに、手でふれてみて欲しいと思います。そして使ってみてください。外見ばかりでなく、内なるものに気を配って見てください。きっと内面や感性を高めるきっかけを陶器は与えてくれると思います。