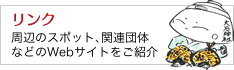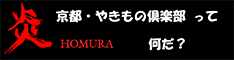「継いでくれなんて、一度も親父からは言われたことはなかった。それに、小さい頃は親父が嫌で嫌でね…」
京都を代表する陶芸家、谷口良三氏を父に持つ正典さん。昼間は陶芸の講師、仕事から帰ると作家活動のため工房にひきこもる?陶芸一筋に生きた父親は、幼い正典さんにとって、陶芸しか頭にない人間。自分は二の次、三の次で、どちらかというと邪魔な存在だったという。
「あちこち動き回らんように箪笥の取っ手に紐でつながれた、なんていう思い出もあります」
いつの頃からか、そんな父の姿を受け入れる。父親としてではなく、陶芸家としての生き様を、正典さんは理解したのだ。
「親父には陶芸だけなんですよ。そこまで情熱を傾けられる凄さを感じましたね」
その情熱を受け継いで、今、自らの意志で同じ道を歩む。大学卒業後、正典さんは父に弟子入り。師弟関係は、20年以上、父の死まで続いた。
「継ぎたいと話したときも親父は何も言わんかったし、弟子入りしてからもほとんど言葉を交わさんかった。でも、見て、感じて、多くのことを学びました。ええ経験させてもろたと思てます」
正典さんは、10年をひとつの区切りとし、それぞれテーマを設けて創作するというスタイルをとる。
以前から続けているのが、「色」にこだわること。「空と雲と風」をテーマとし、「紫紅釉(しこうゆう)」という自ら生み出した釉薬を使い、自然が織り成す色目を陶器に表す。
その「色」に並行して、新たに挑戦しているのが、「土」。
愛媛県の山に赴き、土を採取。粘土つくりから始め、「緋幻釉(ひようゆう)」という自作の釉薬を用い、陶器へと完成させる。
“何にこだわるか”で、同じ壺や花器、茶碗を作っても正典さんの作風はガラリと違う。幾層にも重なり、優しく溶け込んでいく「紫紅釉(しこうゆう)」が繊細な造形を形作るのに対し、採取する土に任せて成形する「緋幻釉」は、骨太で大胆。
「同じことをしてると飽きてきますやろ。作るからにはいつも違うもんを、と考えるんですわ」
「次、どんな作品がみれるんやろう」と、毎回私の展覧会を楽しみにしてくれる人がいます。
新しいことに挑戦することは、その分失敗も多く…。土というテーマで、初めて粘土作りを経験したときは、電話一本で簡単に注文できる粘土が、半年間という長い月日を経て創られるのだということに、改めて気づかされました。
けれど、そういう風に失敗や驚きを重ねてこそ、完成したときの感動は大きい。窯出しの瞬間は、楽しみと緊張が入り混じり、いつも手が震えます。
その手の感覚を失わない、挑戦者でありつづけたいと思っています。