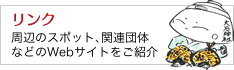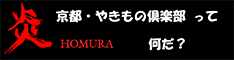「これよりひがし五条坂」と記した小さな石碑が、五条通り、大和大路の東北の角にある。五条坂はその界隈のやきものの町の呼び名でもある。戦前の五条坂は道幅四メートルたらずの道であった。昭和二十年の終戦間際の強制疎開によってその南側の家が撤去され今はもはや昔の面影は想像できない。その小さな石碑が五条坂一帯が登り窯を要した一大陶業地であったことを偲ばせてくれる。
「今では、想像もつかないが五条坂はやきものがあっての共同体の町であった。やきものは勿論のこと、その製造に関連する無数の業種の人達が住み、そして、生活に密接に関りのある多数の店が存在するコミニティが成り立っていた。」祖父の代より五条坂の地でやきものに携わり、自らもその道に進んだ森野泰明さん。自然と家業を継ぐことになった原点は、五条坂に生まれたことにある。
「子供の頃は、窯場も含めた五条坂が遊び場。土の材料の性質とか、やきものの創りの養分みたいなものが無意識のうち自然に吸収できた場所でした。家業を継ぐとか意識せず、自然の流れでやきものの世界に入りました。」京都美大卒業後、単身アメリカへ渡り、大学で陶器講座の講師を三年半担当した。人種も考え方も違う新しい環境は、自らの作風に影響を与えたという。
「京都、パリ、ニューヨークと時間的には同時代性という横糸はあっても、同地域性ではない。作り手の背景にそれぞれの地域の特色がなければ個性は存在しないし、そこに住む必要がない。そこから何が発信できるかどうかが問題です。自分の血の中に引きずっている京焼きの美意識のDNAをあえて否定することなく、自分なりの世界を自分なりの言葉(作品)でかたっていけば、自分なりの新しいものが出来ていくと考えます。それが国際化につながるのではないかと思う。」
森野さんが、作品を確たるものにしたのは、四十歳手前のことだという。
「それくらいの月日はかかります。自分のものができるというのは、イメージ通りに近づけるということ。やきものは窯に入れて人間の手を離れるからね。他人の使った釉薬でなく自分の釉薬を用いたいし、現代の自分の色をと思うから莫大なテストをします。フォルム、材質感、色彩、装飾のすべて互いに響きあい、一体感をもって緊密に結びつく。このような作品をと考えて制作をします。しかし、やきものは不確定要素が多く、うまくいったり、失敗したり。そこはギャンブル性があって、面白いところ。」
手びねりで形作られていく丸みを帯びた温かいフォルム。装飾的でありながらかつそのフォルムをなぞるように描かれる模様。そこに火の洗礼を受けて、焼きつけられた色彩が一体感をなす。土と火という人知の及ばない自然の産物に対して、この調和を実現させることは並大抵のことではないだろう。
やきものは、素材が土と釉薬と炎と非常に限定される世界です。材料があって、工程があって創る。我々のやきものは、手仕事であり、工芸です。工芸は人間が生活する空間に存在し、関りあい何かを醸し出していく。やきものを通して私の空間と誰かの空間が出会う。その時伝わるかどうかですが、・・・・・・。
やきものを無理にこう見ないといけないといった薀蓄はなしに、その人その人の感性で、 好き嫌いを決めるのです。その上で、どんどん多くのやきものを見て、好きになってもらい、そして、やきものの良さをわかってもらえたらいいですね。