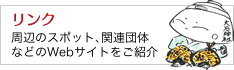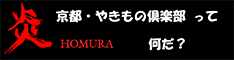祖父の代より九谷から京都へ移り、昭和30年代に作陶地として栄えている泉涌寺にて独立開窯した父親を持つ宮本博さん。
父親の主な仕事は、京焼の代表格である仁清・乾山などの生地を焼き窯元として抹茶茶碗、花器、香炉などの茶道具を中心に作陶し、とりわけ得意としていたのは、仁清抹茶碗だったという。
宮本さんは、少年の頃より手伝いを始め、高校は美術高校の陶芸科に進んだ。その経歴から、家業を継ぐことへの固い意思が感じられるが、本人は意外にそうでもないと首を振る。
「“陶芸家になるんだ”というような、大きな意思は持ってなかったですよ。なりゆきでそうなったという感じです。高校も、勉強が嫌いやったんで、陶芸を選んだというだけ。」
卒業後は1年間、工業試験場で釉薬を学んでから、家業を手伝うようになった。おそらく、そのまま続けていくだけでも生活は成り立っただろう。だが、20歳の頃、宮本さんは、自身の言う「なりゆき」から離脱する。陶芸家としてより強い意志を持つようになったのだ。
「ちょっと反抗心もあったんでしょうね。親父とは、ちょっと違うこともやってやろうと。このまま仕事やってても面白ない。かといって他のことができるわけやないから、今できることは何やと。そう考えたとき、展覧会に挑戦してみようと思ったんです。」
外からの評価で生まれる刺激は、自身の作陶に広がりを与えた。窯元としての仕事の要求も増え、父親が手掛けたことのない、大物の壷などにも応えられるようになる。家業にとどまることなく、独自性を見出していったことが、宮本さんにとって面白みへとつながっていったのだ。
「評価されることに怖さはありません。20代のやり始めた頃は、葛藤がありましたけどね。どうやったらええのか、これでええのかと、随分悩みましたけど。今は、あんまりないんとちゃうかな。徐々にそんな気負いからは、開放されていましたね。」
宮本さんの創作スタイルは、土を彩色し色土にしたものを、成形の段階で模様として表していくこと。途中で曲がっていたり大胆に歪めてあったりと、全体の形は変形したものが多いなか、しっかりと均整がとれているのは、手ロクロの技術が優れているからこそだ。
「ロクロは、丸を綺麗に作るための器具なので、歪な形を作るのには手びねりが向いています。でも、私の場合、形の制限にとらわれず、今までやったことのない形をロクロで表現したいというのがあります。思いきって切ったり曲げたり、ヒビや傷が出ないように気をつけますが、失敗もよくあります。」
「好きなことをやってんのかなと言う気はします。苦しくもないし、何時間やってても飽きないし、これでいいということも絶対無いし。できてしまったら、手放したくないという作品は今のところない。明日、焼きあがる作品を手元におきたくなるのかもわかりませんけどね。」
大切にすると、陶器は残ります。残そうと思えば、100年もそれ以上も。だからこそ、責任を持って作らなあかんと思っています。
買ってくれた方が孫の代まで使っていただけたらいいなと。そう思いながら、作っていきたいと思います。