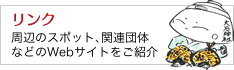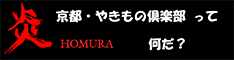高名な磁器作家、市川廣三氏の長男として生まれた市川博一さん。その環境を自然に受け入れ、土と親しんできた。学校の課題で陶器を出品すれば受賞するという少年時代を過ごし、大学は名門、京都市立芸術大学にストレートで合格。全てが順調で、さあこれからと言う時、急に足が止まってしまった。
「周りの学生は、ものすごく勉強して入って来ていました。芸術論や美術用語が飛び交う中にいて、私はちんぷんかんぷん。“芸術的な表現”とか“作品を作る”となると、どうしていいかわからないんです。なのに、粘土をロクロの回転になじませる“土殺し”などの技術は、初心者なら一ヶ月くらいはかかるところを初めから戸惑わずにできた。引け目みたいなのを感じて、僕はちゃんと陶芸やりたくて大学入ったのかどうか、悩みました。」
それは、大学院を卒業した後も続く。非常勤講師を1年間経験し、父親の工房に入った後もだ。そんなとき、信州の先輩の家に身を置いた。陶器のことを一切考えず、気ままな旅を続けた。お金が底を尽きかけたとき、自分に問いかけた。ここで働くか、京都に戻るか?
「ここにいても道は拓けへんから、京都に帰ろうと。戻ると、公募展の期限が迫っていました。そこで、もう一度やってみようと思ったんです。そこからですね、作品を作れるようになったのは。今思えば、信州の旅がいいきっかけでしたね。陶器のことを全く忘れて頭の中を真っ白にすることができた。いい意味で吹っ切れたんでしょう。」
葛藤から解き放たれたように、市川さんは陶器と磁器の両方の世界を手掛け、創作活動にのめり込んで行く。29歳の頃からは、個展活動も展開するようになる。
「個展のきっかけは、先輩に“そろそろ個展すればどうや”と勧められたこと。“もうちょっとまとまったらやりますわ”と答えると、“あほやな。まとまったらするんと違う。するからまとまるんや”と言われたんです。その言葉を聞いて一週間以内に画廊を申し込んでました。いつまでもぐずぐずしてた自分の背中を押してくれたんです。」
個展を積極的に展開することで、公募展でも頭角を現すようになり、“落選か入選か”が、“入選か受賞か”へと変化していた。それは、ちょうど自分の中で納得のいく作品が出来るようになった時期でもあった。陶器において「釉彩」という技法を市川さんなりに見出したのだ。釉薬と釉薬で模様を作ろうとすると、色の境目が滲み、ぼやけてしまうところを、色と色との間にテープを張り、塗り分けしていくという「釉彩」の手法を用いれば、色の境目をシャープに出すことができた。
市川さんは、独自に生み出した技法を「偶然出来たこと」と話す。だが、そこに至るまでの苦悩やもがきは、計り知れぬものがあったのではないだろうか。
「毎日悶々として、イライラしていた時期が何年もありました。若い頃は一体何やってたんやろうって、思うこともあります。今は自信があるかといえばわかりません。作品作りには、今でももがき苦しみますね。」
現在は、個展を中心に活動する市川さん。妥協を許さない自分との闘いは、これからも続いていく。
やきものの世界は奥が深いです。弟子を取る立場になった今、陶芸を志す方に伝えたいことは、やきものの上っ面だけを見ないこと。形から入るのではなく、やきもののルーツの様な基本的なことを知ってやったほうがいいということです。
無駄と思っていることであっても、幅広くやきものを知ることは、積み重ねになると思いますし、それが、思わぬヒントを生むことになるかもしれません。役立てようと思ってやるのではなく、とりあえず何でもいいし、やってみる。それが何らかの形でいつか返ってきたりする。返ってこなくても、話のネタになるだけでも良し、という感覚で、関心を向け挑戦していって欲しいと思います。