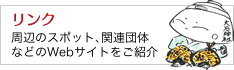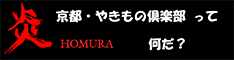「学校では、絵も工作も下手で不器用。根気もなく、どんくさかったですよ」。創業90年あまり、陶器などの美術工芸用木箱を手掛ける森木箱。未来の四代目、森久杜志さんのこの一言に驚いた。
昔から“門前の小僧”という言葉があるように、ものづくりの家に育った人間は、天性の器用さというのが自然に備わっているイメージがあったからだ。
「小遣い欲しさに手伝いをしても、相手は職人やからうるさいでしょ。ダメだしを食らうことも多かったから、嫌な世界やなと。継ぐことにも反発してましたね。」
だが、そんな森さんも、気がつけば父と同じ道を歩んでいた。 「やっぱり、何やかやと手を動かすのが好きやった。立ち止まってよく考えたら、家が手作業をやっていた。そこの道から自分の作りたいもんを探っていけたらええかなと思ったんです。」
物を作る喜び。器用さ以上に大切な精神が、性分として受け継がれていたのだった。不器用もまた森さんにとっては、ものづくりへの探究心を掻き立てる道具となる。
「器用やないから何とかしようと思って、工夫していくうちに自分のもんができていくんやと思います。最初から上手なやったら努力せんでしょ。父に習って、ある程度できるようになるのには、10年はかかりましたが、器用だったら人より簡単にできてしまうから、かえってつまらなかったのではと思いますね。」
森さんは、受注生産で美術木箱を手掛ける傍ら、作品制作にも力を注いでいる。美術木箱は桐、杉、モミが中心となるが、作品用は材木屋から集めてきた端材が素材。ケヤキ、黒柿、赤杉、ウォールナット、黒檀、神代杉など、その時々に出会った端材を使い、手を動かしながら、椅子、タバコ盆、電話台などの作品に仕上げていく。
「木は生きているもんでもあるから、繊維の密度も木目もそれぞれ違うし、木の性格も違う。自分の言うことを聞いてくれるわけではないので、木と話をし、気を使いながら、思い通りの形に近づけていかねばなりません。」木目や癖など、その木の雰囲気を見ながらデザインや遊びを加えていくのが森さんだ。それが、物を納めるための木箱に留まることなく、単体で主張する存在感を生む。最近では、草木染の染料で木を染めたり、他業種の研究会に参加するなど、木の可能性を探る日々だ。
「既成のものだけではなく、全く違う素材とコラボレーションして一つのものを作るのもいい刺激です。時間も材料ももったいないことかもしれませんが、形のないものを形にしていくというのが面白いし、できあがったときの達成感がある。山登りで登りきった瞬間のような感じが好きですね。」
最近、桐箱が格安の値段で売られているのをよく見かけます。職人ものと大量生産品を、ぱっと見では見分けることができないかもしれません。決定的な違いが現れるのは、年数がたってからのこと。大量生産品は木目や繊維を無視して作られているため、歪みが生じ、表面がでこぼこしてきます。職人の作るもんは、木の性質に合わせながら手を施していくため、年数がたってもほとんど狂いません。
違いが分かるのが、買う瞬間ではないため、職人ものはなかなか目にとまりにくい。それでも、職人が作るものが全く別ものであることを、使い手の方が感じてもらえるように作品作りを続けていきたいと思います。