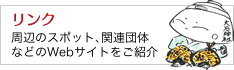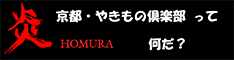寛永年間に京都に創業し、初代が生み出した緋銅色、黄銅色の金属着色法が初代の通称「五良三郎」を取り「五良三色」と世に聞こえて以来、金谷家(※初代の屋号は「金家」。9代目より、「金谷」と改めた)は、代々「金谷五良三郎」を襲名する金工の名家である。
当代の金谷さんは、平成17年より兄からその名を継承した15代目。父親の13代目は高岡出身で、金谷家の血筋になかったが、技術継承を重んじる金谷家にあって、その技術力を買われての抜擢だったという。「金谷家の仕事を彫金師の父親が手伝っていた縁で、後継を請われたそうですが、当時は終戦直後。戦争で金属は全て軍部の供出にあい、道具も何もかもなかった時代でしたので、最初は継ぐのに気が重かったと、父親が言っていました」
金谷さんは、小さい頃から遊びながら金工に親しみ、継ぐことにも違和感はなかったという。高校生の時には早くも日展に出品。斬新なレリーフは、「時代が早すぎる」として入選こそ逃したが、相当の反響があったという。
高校卒業後は京都の金工師のもとへ5年間修行に出て、鍛金を学んだ。「鍛金を選んだのは、父親の意図もありました。父親は、生地の上に最終的に模様を彫っていく彫金師だったんですが、仕事をしていくうちに、『こんな形の生地に彫りたい』という意志もどんどん湧いて来たんでしょう。息子に形を作れるものがあれば言うことないということで、私に鍛金をやれと。私も、金槌で叩いて思い通りの形にしていく形作りが好きだったしね。金属という固いイメージから、やわらかいイメージへと仕上げていけるのが、金属に命を与えているような感覚になるからかもしれません」
修業期間で、金谷さんが最も時間を費やしたのは、「見る」ことだったという。夜18時に仕事が終わっても家へ帰らず、師匠がやる仕事をじっと見続けていたのだ。「ずっと横で見てたんです。2、3時間はへばりついて見てましたね。師匠からは『なかなか食事に行けへん、早く帰れ』と言われたこともありましたから、迷惑だったのかもしれません。でも、そうやって脳裏に焼き付けてきたことが、今では役に立っています。自分で仕事をしだすと壁にぶつかることが多いんですが、そんな時に、あの頃のことがぱっと思い浮かぶんです」
修行後はさらに1年間、東京で機械成型の「へら絞り加工」を学び、家へと戻ってきた金谷さん。父親は彫金、金谷さんは鍛金、後に兄の鋳造が加わり、分業が主流の金工の世界において一貫生産のできる金工工房として、華道花器や抹茶煎茶道具など、あらゆる金属工芸品を手掛けてきた。15代を受け継いだ現在でも、息子さんと二人で鍛金、彫金、鋳造まで一貫制作でこなしている。
「茶道具は形の決まったものも多くて、飛びぬけたデザインをしてしまうと茶室に合わなかったり、他の道具とのバランスがとれなくなったりします。その中でできるだけ暴れようと、自分なりに変化させて目新しくなるように作っています。」
常に他にはない独自性を求めて創作する姿には、寛永年間創業という金谷家の歴史が、技術継承で保たれてきたことが背景にある。
「これまでの代以上のものを作りたいという思いはありますよ。そう思って初めて、その代の特徴が出てくるんやと思います。ただ同じことをするような単なる継承では仕方がないですし、自分は自分のやり方で、色にも形にもこだわって、違った特色を出していきたい。自信のもてるものをどんどん作りたいですね」
その意志は息子さんにも受け継がれているのだろう。より繊細な型取りができる蝋型鋳造を独自に勉強し、新たな金谷家の技術として加えているのだ。
「今は、金工の需要が減少しており転換の時期でありますが、それが新しい技術を取り込むきっかけにもなり、新たな仕事を生むことにもなる。そう考えながら、時代の浮き沈みに代々耐えてきたんでしょう。技術の開発というのが、何より金谷家の続いてきた秘訣なんだと思います」
金工品は面白い。使い込めば込むほど、古くてええ味になっていきます。金谷家の作品かどうか鑑定の依頼が時折ありますが、その中で、素晴らしいと感じるのは、持ち主が手入れしてあるのがひしひしと伝わってくる作品です。逆に、どんなに技術はしっかりしていても、ろくに手入れがされていない作品は、見ると残念な思いがします。
持つ人次第で、金工品は変化します。その変化は、計算できるような範囲ではなく、私であれ機械であれ、意図的に作りだせるものでもありません。使い込まれてきた階段の手すりのような、時間と人の手のみが叶えてくれるやわらかい艶。それが、金属にはあるのです。
何でも新しいものを使い捨てる時代にあって、色が変化する金属は時代遅れかもしれません。けれど、かつての日本人は、そんな変化に面白みを感じ、物を大事にしてきました。そういう変化を楽しめる日本人が、現代に一人でも増えていってくれればいいと願っています。