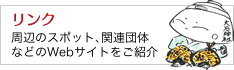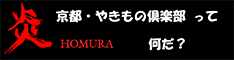「私はそもそも、すごく不器用なんです。技術を覚えんのも遅くてね。繰り返し繰り返しやって、少しずつ身につけていくんです」清水さんのこの言葉に、最初はピンとこなかった。
職人にとって、手先が不器用である ことは、致命的であるように思えたからだ。だが、その先に続く言葉に思わず膝を打った。
「陶工訓練所に入った時、先生に聞いたんです。入所させるのに、どんな基準で選んでいるのかと。そしたら、『器用な人は入れない』という答えが返ってきた。器用な人は簡単に何でもできてしまうから、簡単に忘れもする。不器用な人はできないものだから、しつこく何度もやるでしょう。時間かけんと覚えられないということが、結果的に体で覚えることになると」不器用であることを、最大の武器にする。清水さんはそういう職人なのだ。瓦職人から陶工へと転向し、尚泉陶苑を開窯した父親の後をごく当たり前のこととして継ぐ道を選んで以降、訓練所や工業試験場へ通い、土と格闘しながら習得していった「父は一般食器の仕上げの工程を担う職人でしたが、私はろくろをやろうと思いました。思うように作れなくて、苦しい時期もありましたね。でも、腕が上がっていくような雰囲気のある瞬間もあって、その時は作るのが面白くなる。苦しい時と面白い時を交互に繰り返しながら、覚えていきました」卒業後は、すぐに父のもとで働いた。技術を教えてもらうことはなく、見よう見まねで技術を盗む。一切を任されるようになったのは、30を過ぎてのことだった。
尚泉陶苑では、茶碗や急須、とっくりなど、料亭向けの一般食器を中心に扱っている。清水さん曰く「しつこいまで」に技術を身につけた月日は、食器であればどんな形でも成型できる職人へと清水さんを成長させた。オーダーメイドにも対応できるのも、清水さんの実力の高さを物語っている。
最初の工程であるろくろの成型を主に手がけ、絵付けなどは別の職人に依頼するため、それぞれに携わる職人同士のイメージの合致には気を使う。 「どんな絵柄にすればよいかはこちらで指定しますが、この指示が結構難しい。自分で自由にならない分、イメージがうまく伝わるように正確な指示が必要なので、若い頃はそれをつかむために、植物園にスケッチに行ったりもしていました」分業制であるがゆえの歯がゆさはあるが、それらがぴったりとはまったときは、何より良いものができる。
「イメージ通りにいったときは、嬉しいですね。ろくろの形にしても、ほんまに納得できるのはほとんど無いに等しい。いい時もあるし、なかなか思うようにならない時もありますが、常に納得いくまでやる」
「二代目として、自分らしい特徴を出したい」と、仕事を任されてから作り始めたのが、「南蛮焼」だ。土と炎がそのまま反映された焼き締めの色が、清水さんのこだわる造形美を一層引き立たせる。
「登り窯のような焼き締めの色を目指しています。今はプロパンガスですが、そんな色を表現するために焼成の12時間は、ほとんど寝ません。最後の3時間は特に目が離せない」
季節によって、その時の窯の状態によって、色が思うように出ない時があるため、やり方をノートに書き留めても徒労でしかないという。毎回毎回、方法を探りながら、イメージに近づけていく。
「まるっきり勘の世界ですが、焼き上がって納める時に、まったく首をかしげんような状態で納められた時が、一番嬉しいですよね。何百個と納めるとき、ひとつひとつを見渡してみて全部納得できるのが理想です」
一度に同じ商品を百個単位で納めることが多い食器の世界において、長く使われるためには、使いやすい形であるかどうかが求められます。昔から受け継がれてきた伝統ある形は、使いやすいからこそ今に残っているのだと思いますが、ただ真似るだけではつまらないので、少し形を変えたり、筋を入れたりして自分なりのアレンジをします。少し変化をつけるだけでも雰囲気は変わる。使いやすさと変化のバランスが備わった形を求めて、常に勉強の毎日です。