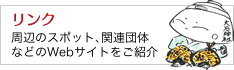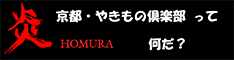指物師高田昌典さんの家は古く、徳川の初期から続いた家で、昌典さんは18代目にあたる。高田さんの層祖父が、農林省(現在は農水省)において転勤の多い官林の払い下げ事業に従事し、その息子で高田さんの祖父、初代高田正臣氏は転勤続きの生活のなか青春時代を過ごした。土地にようやく慣れた頃に、親の都合によって土地を離れねばならない境遇が寂しく、「将来は土地に根を張れる仕事を」と、官職には目もくれず、指物師として生きることを決意。京都で修業をした後、大阪市で大正8年「指物師高田」として開業。当時は、軸箱を中心に手掛けてきた。
大阪大空襲から命からがら京都へと逃れ、戦後京都で店を再興した際も、大阪の客は離れることなく、再興当時は大阪の客が大半を占めていたという。
戦前からは、商品を軸箱から茶道具へと転換。高田さんもその流れを継ぎ、茶道具を中心に受注生産にて制作をおこない、また古い茶道具の修理も多く手がけている。
「最初から後継ぐもんやと思ってましたね。後継ぎは私一人しかいないし、まわりからも物心つく前から完全に後継ぎやと言われてました。小学校6年生からは、仕事場の掃除が日課でした」
高校卒業後、父のもとで修行を始めた高田さん。いったん仕事場にはいると、父と息子の関係性はなく、師匠と弟子だ。
「父は最後まで仕事一筋の人でした。病を患って一線を退いても、2階の仕事場で私が仕事をしていると、木釘を打つ音を聞いて、『こら、なんちゅう仕事してる』と1階からかけあがってくる。晩年は、突発性難聴で耳は聞こえなかったはずなんですが、それでも音を聞きつけて、どなるんです。空気の振動みたいなものなのか、感覚的にわかるのか、すぐに『ちょっと降りて来い』と1階から声が飛んできました」
最初の3年は専ら下仕事で、木釘すら「お前には勿体無い」と言われ、自分で作らねばならない。高田さんは兄弟子や父が仕事場に残した廃材を集めては、かんなで削り直し練習に打ち込んだ。
「修行中、よい仕事ができる時がある。けれど、親父に言われたのは、『波をなくせ』。調子のよいとき、悪いとき、その波ができるだけ小さいほどいい。仕事するうちに手が枯れてきていちばんいいところで収まるから、そこまでいかんとあかんと」
そう言われても最初高田さんはピンと来なかったという。わかり始めたのは、30歳を超えてからだった。40代に入ると、どんな仕事に対してもそう言えるようになったという。
それでも、木を相手にする商売だ。木は生き物で、二つとして同じ木はない。その木を使うのは、経験と勘次第だ。
「木の仕入れは40手前から、始めました。木をある程度扱っていないと到底できません。それでもよく失敗しましたよ。材木屋さんへの高い授業料やと思うしかない」
父の2代目正彦さんが遺してくれた木もある。父亡き後、高田さんにとって父の木はなによりの財産だ。
「とびきりいいのがありますよ。よすぎて、いつ使おうか、まだ決められません」
そう言って、高田さんは木を愛おしそうに眺める。
いつ使うのか、その日が明日なのか遠い未来なのか、いつ訪れるかはわからない。
確かなのは、高田さんが最高の木を使い、最高の仕事をするのだろうということ。
想像をめぐらせると、高田さんの木を無心に削る姿が、鮮やかに目に浮かんだ。
大量生産、機械製品、廉価商品が出回るなか、手作りの指物に対して、それらの製品との値段の違いに驚かれることがあります。外から見れば確かに違いがないように見えるかもしれません。
違いをいうならば、機械では同じものは作れますが、手作りは同じものが二度も作れないということ。木は使えるようになるまで最低三年以上寝かします。仕事を始める前には、全て頭の中で出来上がりを想定します。
手作業から生まれるものは、同じ商品でも違った雰囲気がそれぞれにある。言葉ではうまく表現できませんが、そんな大量生産品とは違うものを、自分の手で作ることに、面白みとやりがいを感じています。