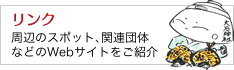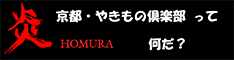一般食器用の木箱を手掛ける工房に生まれた小野賢太郎さんには、木の音とともに育ってきた記憶がある。1階は工房、2階は家族と住み込みの職人の住まいという食住一体の環境は、常に1階から木を削る音が聞こえていたためだ。幼少時代を送った昭和30年代、工房は目が回るほど忙しく、夜中を過ぎてもその音は絶えることなく、小野さんは子守唄のように聞いていたという。
「音がないと逆に寝られないくらいでした。当時は職人さんが6、7人ほどいて、寝る時は雑魚寝状態。そんな環境で育ってきたので、家を手伝うのも自然な流れでした」
中学卒業後、家業を手伝い始めた小野さん。仕事は教わるのではなく、「見て覚えろ」の世界だったが、父親や職人の姿の仕事ぶりが幼い頃から目に焼き付いているため、技術を身につけるのもそう難しいことではなかった。矢継ぎ早に舞い込む注文に追われるなか、趣味のスケッチが息抜きとなった。
しかし、そんな多忙な日々も、国内産の安価な大量生産品に需要を奪われてからはめっきり減ってしまう。
「今から20年か25年ほど前からでしょうね。機械化が進んだおかげで、職人技を身につけなくても、誰でも機械を動かせば作ることができるようになってしまった。私の工房も一部は機械化しましたが、ほとんどが手作業のまま。父親の代まではそれでもなんとか仕事は得られていたのですが、私の代になると、より大規模に木箱作りをする工場が次々に生まれ、数と値段ですぐに太刀打ちできなくなりました。職人さんも徐々に辞めていき、今では私一人になっています」
どの方向から入れてもピタッとはまる。角型の木箱において、手作業で面と面をきっちり90度に仕上げるのは難しい。
「一か所でも歪みがあると、箱が納まらないので、正確に角は作らないといけません。しょせん箱とは言え、手で作るのは骨が折れます」
その難しい作業をこなしてきた技術の蓄積が、小野さんの新しい活路を開くことになった。大量生産品と同じ土俵で戦うのではなく、大量生産品ではできないものづくりをすること。つまり、一品ものや誂え品の注文へと仕事の転換を図ったのだ。
「茶道具関係の方から、『こんなんできへんか』と相談を持ちかけられて、受けるようになってから、誂えの注文が増えてきました。今まで作ってきた木箱は寸法が大体決まっていましたが、誂えものは図面もないようなところから始めます。どうやって作ろうか、お客さんと摺り合わせしながら作っていきます」
ただ作るだけが終わりではないという。そうやって出来上がった商品がお客の満足を得られるかどうか。次の注文へとつなげられるかどうかを見越して、ものづくりをする。
「次の注文をもらえるように、きっちりしたものを作る。下手なものはお客さんには渡せません。見る人が見たら、あかんと言われるようなものを作るんではなく、誰が見ても綺麗にできている、そう言われるものを作り続けていかないといけません。結局は、自分がいいものを作るかどうかです」
誂えものの仕事は難しいものが多いです。それゆえに、何度も作りなおしてようやく出来上がる時の嬉しさは大きい。「小野さん、ええ箱作ってるね」と、お客さんに喜んでもらえる時、「いいものができた」という声を聞く時に、やりがいを感じています。