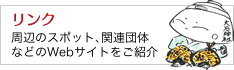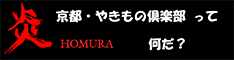木箱職人を父に持ち、高校卒業から、自らも職人としての道を歩み始めた小島登さん。
「継ぐことにそんなに抵抗はなかったですね。半分義務的な面もあったかもしれませんが、ただ、小さい頃から木が好きでしたから。」
仕事を始めた当初は、陶器用の木箱が95%を占めていた。しかし、10年ほどで、50パーセントへとシェアが変化してしまう。価格の安い中国製の木箱が大量に日本に入ってきたためだ。その変動に伴い、小島さんは自分の技を磨くため、日本伝統工芸展など、芸術分野へ出品し始める。
「同じことを続けていても仕方がないなと。自分も勉強して、広がりをもっていかんと、変わっていかんから。」
そこで入選を繰り返し培ってきた力が、今の小島さんを生んだのだろう。人間国宝の作品を納める木箱や、文化財を保存する木箱制作を中心とする職人へと小島さんは自らを変えたのだ。
「新しいものに挑戦するのは、得られるものがあるからなんです。ひとつ作り出すということは、2つ、3つもまた新たな発想を生み、展開を生みますから」
全国の職人を回り、断られ続けた三味線の道具箱の制作を、引き受ける程の実力を持つ小島さん。
「見本を見れば、どうやって作ればいいか、頭に浮かんできます。ただ、制作で面白いのは、十人職人がいたら、十人ともやり方が違うこと。それぞれ自分のやり方というのがあって、自分で手順を見つけていくんですよ。」
見本はあっても手本がないのが、木箱だ。正攻法は、自分で発見する。
小島さんが、殆どの工程で使うのは、さまざまな種類のかんな。面の角度を出すのも、蓋の噛み合わせの窪みを作るのも、ふんわりと丸みを帯びた曲面も、かんなで削るという行為によって導き出される。四角形、六角形、八角形・・・どんな形をした箱であっても、すべての角度を、削ることによって、寸分の狂いもなく仕上げていく。
そんな手業の光る木箱は、どこから上蓋を乗せても、手の力で押さえることなく、重力に従って静かに下りていくように、閉まる。かんなで磨かれた面は、桐でありながら、宝石のように、光の角度でキラキラと輝く。
「狂いない仕上がりを、手で作り出すことが、私の仕事。休みも取らず、忙しい忙しい言いながらも、続けてるのは、やっぱり好きだし、面白いからですね」
中身があっての箱、箱があっての中身?私は作るとき、いつもそう思うように心がけています。箱は、独り歩きするものではないし、一人舞台で活躍するものでありません。
着物と一緒で、中に着る人があってこそ輝くものだと思っています。だから、一番気をつけるのは、その中身と雰囲気をあわせること。中身がやさしい雰囲気のものであれば、やさしく、丸みを帯びた感じに、ごつごつした力強いものであれば、角度を鋭くした感じに・・・この世界に同じ木目、形の桐は存在しないように、私から作る木箱もまた、ひとつひとつの雰囲気を表現していきたいと思います。