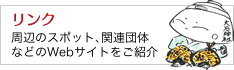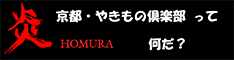ただ深々と品格が漂っている。あからさまではなく、つつましい。気取らずに、朗らかである。伊東慶さんの白磁には、そんな形容がよく似合いそうだ。
陶芸家伊東翠壷氏の長男として生まれ、「長男は家を継ぐもの」と、陶芸の道に進んだ伊東さん。京都美術専門学校(現京都芸大)に進学し、弱冠19歳で第6回新文展に初入選。「自信はありました。出したら入選するつもりで、何年もかけて構想を練り、仕事をしていましたからね」。その後、徴兵のため中国の大同へ出兵し、復員後は楠部彌弌先生が主宰する「青陶会」の門下生となった。伊東さんを始め気鋭の陶芸家20名以上が毎日のように議論を戦わせ、技術を磨き合ったという。
「楠部先生には一言、二言を言われるだけ。それで分かるんです。自分の作品の欠点をずばり見抜かれているということをね。あれこれ言わなくても、その一言で全て修正ができるような実力者が青陶会には集まっていました。日展入選はもちろん、審査を任される人間もいましたから、それぞれに秀でた技術がある。それをお互いにぶつけ合い、高め合ってきたんです」。
夜になれば先生に付いて祇園へと繰り出し、「先生のツケ」でよく遊んだという。京都画壇のサロンにも顔を出し、そこに集う一流の文化人と顔見知りになるなど、遊びのなかから人とのつながりもできてきた。そこから作品も広く知られるようになり、評価も高まってきたという。
「若い時はわからずに遊んできただけですが、結局はそういった遊びのなかでの付き合いが、作品に格を与えてくれました。技術は勉強するもので、格は周りが作るものなんですね。お金に物をいわせるのではなく、人と人とが一緒にどれだけ遊び、喧嘩をしてきたかということ。作品はそういう様々なつながりから、確立していくものなんだと思います。京都はそういうところで回っている。現代は少し違うのかもしれませんが、私はそういう時代に生きてきましたよ」。
伊東さんが白磁へと情熱を傾けるようになったのは、30代の頃だという。以来50年以上にわたって、白磁と対峙し続けている。
「白磁は陶芸のなかで最も難しいとされています。その難しいものにあえて挑戦することが魅力ですね。焼き上げた時に、わずかでも黒い鉄粉が出てしまえば失敗作になります。鉄粉は空気中などどこに浮遊しているかわからず、それこそ偶然混入してしまうものですから、技術的には失敗ではないかもしれません。でも、白磁への憧れや白く完璧なものを作りたいという思いが自分のなかにありますから、納得いくまで作っています」。
作品のテーマは、散歩したり景色を見たりして生まれてくるものだという。庭の植物や川の流れ、様々な事象に、伊東さんは絶えず観察の眼を向けている。
「そうやって考えているのが好きなんでしょう。日展は62年間、出品し続けていますが、2年先くらいの出品作のことは考えています。そうしないと楽しみがない。私にとって考えているということ、作るということは遊びなのかもしれませんね」。
川の流れに同じものはありません。回ったり、どこかで滝になったり瀬になったりします。そんな景色の移ろいを見つめながら、作品を作り続けてきました。作陶を始めてから長い月日が経ちましたが、振り返れば好きなことをやってきた人生だったという思いがします。この先も作り続ける限り、その思いは変わらないことでしょう。作る楽しさ、白磁の難しさに面白さを感じながら、これからも続けていきたいと思います。